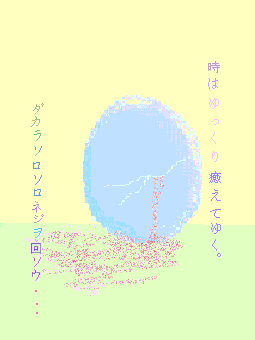 Special thanks...Shinobu Yoshizumi
Special thanks...Shinobu Yoshizumi赤い砂が床にこぼれていた。
遠くから見た時、それが血に見えて一瞬目の前が光に刺されたように痛んだ。けれど実際、その赤はチカチカと光を撒いており、そのため濡れているように見えたのだろう。鮮やかな赤は見覚えある砂で、瞬いているのはガラスなのだと判った。
机の隅にある筈の砂時計がない。ぐるりと部屋を見回すと、案の定砂時計の枠が椅子の脚もとに転がっていた。ゆっくりと板張りの床を踏みしめて歩み寄る。
「つ、」
右足の小指がちくりとした。用心したつもりがガラスの破片を踏んでしまったらしい。そこにあった真新しいクッションを部屋の隅へと蹴飛ばして道を開け、片足でベッドに辿り着いて腰掛けた。
右の足首をつかんで小指を確かめる。傷口は見てから初めて、ひりひりと痛みだす。空いた手の指に唾をつけて傷口を撫でた。
天気予報のテーマミュージックが七時半をまわったことを知らせた。ブラウン管に映し出された東京駅前で、その風景には不似合いなダウンジャケットのリポーターが頬を真赤にして今日の天気を伝えている。その後ろを足早に行く人々は暗い色のコートの背中を固くして、風を切って歩く様が怒っているように見える。
そんな画面を見つめていると、なんだか責められているような気がして胸が痛い。まだ目が覚めていないのかもしれない。顔を洗って髭を剃る。鏡の中から赤い目が僕を睨み返した。
厚い黒のセーターを着ると、袖口にこびりついた白いアクリル絵具がこの世界で最もやさしく見えた。部屋を出て地下鉄の駅まで歩きながら、右足の小指の傷が痛いような、くすぐったいような感じで不思議だった。決して不快ではないがどこかで気にしている自分が可笑しいような、とても遠い処から呼ばれるのに似ていると思った。
あたたかく明るい地下鉄からホームに降り立つ時、くすんだ壁と湿った床と、目にするたびせつない色彩が僕を現実に押し戻す。もう誰も居ない車両は安堵の吐息でドアを閉め、静寂だけを乗せて走り出す。それが袖口の絵具に似ていた。取り残されたようで急いで階段を上った。
冬だけが持つ太陽の輪郭の曖昧さと、僕の揺らぎは交錯して、透明な織物となって僕の前に延びてゆく。その先にきみの部屋がある。
偶然なのかもしれない。僕は必然というものを見たことがなかった。
運河に架かる橋を越えると、織物は川風に溶けて僕の頭を撫でていった。きみの部屋の戸を叩くまで、何度も何度も、その感じを思い出すよう努めた。記憶の底の、錆びた一本の螺子のようながらくたが今、僕に何か話しかけている。
扉の向こうの、きみの白い頬や肩を思うと今にも名前を叫んでしまいそうだった。
凝縮された祈りのような刹那、額を撫でるあの感触が蘇った。悲しい子供を慰めるような仕種。力づけられてきみの部屋まで駆け出す。古く重い扉を、一回、二回、と叩く時には、もうその無意味さに気がついていた。
現実の僕は僕らしくいつものように、大学で絵筆をとり、帰り道には本屋とレコード店を覗き、スーパーで夕飯の材料を買って帰宅した。奥の部屋の戸は朝のまま開いていて、赤い砂とガラス片もそのままなのが見えた。思い出したように足の小指が疼く。
何もする気になれなくて、スーパーの袋ごと冷蔵庫に押し込もうとしたが、そこにはやはりスーパーの袋がいくつか入っていた。それらを全て出して、ビールやチーズなどを戻し、古い肉や豆腐などを捨てた。煙草がよく冷えていた。このトマトは食べられそうだ。片づけが済むと、トマトを洗ってそのままかじりついた。
砂の辺りを避けてクッションに座りテレビをつける。それからしばらく、CMのたびにチャンネルを変えて、僕は溢れる色彩だけを見ていた。ふいに電話のベルが僕を振り返らせ、部屋中がテレビの残像で黄色に染まった。今度こそガラスを踏まないように気をつけながら受話器をとると、「ああ、居た」と友人の声だった。
「今駅前の、そう、そこにいるんだけどさ、たまには顔出せよ」
「いや、今日はいいよ」
「飯、食ってるか?」
「うん」トマト一個とは言えなかった。
「死ぬなよ」
「ばかなこと言うなよ」
「絶対に」
彼の言いたいことは判っていた。最低限の言葉が何よりも『彼』だった。
「そのうち行くよ、部屋に」僕は言った。
「ああ」
「まだ、絵が途中なんだ。終わったら行く」
「ああ」
二度目の返事は、照れたような笑いを伝えた。
受話器を置くと、耳に残った『彼』が砂を片づけろよ、と言うので「仕方ねえな」と声に出した。
ようやく安全になった床に座り込んで、テレビのチャンネルを変える。抱えたクッションに顎を載せてしばらくニュースを見ていたが、目が疲れて視線を落とした時、白いカバーに小さな赤い点を見つけた。
血だ。
そう思った途端、頭を殴られたような衝撃と、激しい嘔吐が襲った。僕の冷静な部分が、これは朝クッションを蹴った時のものだ、これは僕の血だと叫んでいたが、これは本物の血なのだという事実が僕を立ち上がらせた。ようやく洗面台につかまり堪えていたものを吐き出す。一日にトマト一個しか食べていない僕の吐いたものは、やはり赤いトマトだった。トマトだ、と呟いて、それが呪文のように、トマトだ、と繰り返す。蛇口をひねり迸る水に口をつけた。もう眠ることしか考えられなかった。
湖。
夏の終わりの。目の端を掠め飛んでゆく、緑。
光。太陽の熱と風の冷たさ。臍の辺りが温かい。
手だ。きみの。
と、エンジンの振動が僕の全身を包んだ。
一日は穏やかに回り始めている。山の稜線が近づき、湖が見えた。水面に光の帯が踊る。
歩く。手のひらにきみの指先の感触がある。時々、きみは僕の視線に気づかないふりをする。戸惑って笑いだす。僕も笑った。きみのいる場所は、いつも光に満ちていた。
きみの唇が何かの言葉の形に動く。けれど僕には聞こえない。その不思議に気づかないのは、もうこれ以上その言葉を聞きたくないからだ。『来てよかった』頼むから、もう言わないでくれ。空が僕の足元に落ちた。世界が暗転する。
暗闇に投げ出された僕の体は、耳だけが正常に機能していた。金属が擦れあう音。叫びのように高い音。ボールの弾む音。物の砕ける音。
誰かが明かりをつけたのかと思う程、急に眩しくなる。僕の右脚はバイクの下敷きになっていた。喉に鉛の栓をしたように息ができない。きみを捜す。倒れているきみがやけに遠くに見える。
きみの左手がわずかに動いた。僕に手を差し延べている。手のひらは絵具を塗りたくったように赤かった。
喉につまった鉛の栓を、呼吸を求めて吐き出した。ヘルメットの中で溺れそうになり、震える手でヘルメットを外す。その間、目だけはきみから逸らせなかった。息ができない。喉から熱く流れるものを吐き出しながら、胃の底に落ちてしまった声をどうしようもなかった。
久しぶりにあの時の夢を見た。きみの夢を見た日は声が出なくなる。
汚物にまみれて気を失った僕は、病院のベッドで目を覚まし、きみの死を知らされた。僕は右脚骨折と右腕の打撲で済んだが、退院する日まで喋ることができなかった。一度きみの両親が見舞いに来てきみを返せと言った時も、そしてすぐ「すまない、君のせいじゃないのに」と目を伏せた時も、口を開くことすらできなかった。
右カーブの向こうから曲がりきれなかった対向車が目の前に飛び出してきた。咄嗟にハンドルをきったが、きみを振り落としてしまった。そこへ対向車が突っ込んだのだ…と後で聞いた。その瞬間のことを僕は覚えていない。事故現場に耳だけ残して、僕は居なかったのか。
声を失っている間、外に出られない同じ言葉がいつも僕の中で渦を巻いていた。
なぜ、僕だけがここに居るのだろう。
なぜ、きみではなく僕なのだろう。
それは重く、僕の動きを鈍くした。眠りに落ちる寸前、全身を地面に埋め込まれるように感じながら僕が生きているということが不思議でならなかった。これは死者の夢なのかもしれないと思ったりもしたが、目が覚めると周囲の様々な物質がひどく現実的で(しかもそれは本当に現実で)僕を打ちのめした。
退院の日、彼が車を出してくれた。ぼんやりしている僕の代わりにてきぱきと荷物をまとめた。ベッドサイドのひきだしから、何気なく渡されたそれは、腕時計だった。いつも右腕にはめていたので、ガラスは罅割れ、針は曲がって動かなくなっていた。ひきだしを開けることも思いつかなかった僕が初めて見る事故の跡だった。息が、と思うとまもなく真赤な手のひらで目隠しされた。
シャツの胸が、膝が、生温かいもので濡れた。彼は驚いて背中をさすりながら、「ごめん」とひとこと言った。思いがけない言葉に僕は「違う」と答えた。やっと出た僕の声と、意味の通じない答えに彼は「え?」と困惑した。
僕は答えずにはいられなかったのだ。
違う、と言わずにはいられなかった。それは彼の「ごめん」に対してでもあったし、ずっと問い続けてきた僕に対して、何にせよ答えは必要だったのだ。
課題の提出日が迫っていた。キャンバスを部屋へ持ち帰ってもう五日過ぎている。いくつかの習作はできているが、真白のキャンバスはまだ包みも解かれないままでいる。
スケッチブックを塗り潰すように描き込んだり、紙をくるくると回してあれこれ構図を思案する。コーヒーをいれようと台所に立ち、コーヒーがないことに気づく。今日は三回、同じことに気がついている。
電話のベルがやけに大きく響いた。しばらく鉛筆のさらさらという音しか聞いていなかったからだ。
「もしもし、俺。今から行くから」
こちらの都合も訊かずに彼は言った。僕の方も断る気はなかった。彼は強引さをタイミングを計って使う男だ。
「コーヒーと煙草。あと消しゴム」
「OK」
程なくして彼がやってきた。「雪降るってよ、雪」と言いながらコンビニの袋を床に置くと冷蔵庫を開けて、「うわあ」と呻いた。冷蔵庫の中が明るいのは、白いビニール袋で一杯だったからだ。
「何食ってるんだよ」
「何だったかな」
彼は袋を全部出して中身の確認をして、これはよし、とか、勿体ない、とかぶつぶつ言っていた。ふいに大声で呼ばれた。
「あるじゃないか、消しゴム!」
と、投げて寄越した。両手でキャッチした消しゴムは冷たく、汗ばんだ手のひらに心地好かった。僕が笑うと、彼は「ばーか」と笑い返した。
鍋にたっぷりの水を張って火にかけると、海苔とシソを僕に渡して、彼は明太子を取り出した。
「また明太子スパゲッティー?」
「俺はこれとタラコスパしか作れないんだ」
「同じだろ」
僕は傍らの椅子に腰掛け、狭いテーブルに皿を置いて海苔を鋏で細く切った。鍋の湯が沸騰すると、彼は半分に折った麺を鍋に放り込んで「今何時?」と訊いた。
「時計見ててよ。今から十一分」
「わからない」
「何で」
「時計がない」
目覚ましはタイマーで毎朝テレビがつくし、時間もテレビの画面に出ている。夜には時計など必要ない。かつてこの部屋にあった時計と名のつくものは、腕時計と砂時計、それも壊れてしまった。それでも不自由はない。
彼は僕のカセットラックから適当にテープを取り出してデッキに入れた。フェアグラウンド・アトラクションが流れ出す。「三曲くらいだな」と彼は鍋の中を菜箸で掻き混ぜた。
久しぶりに食事がおいしかった。今度は僕がコーヒーをいれた。その間、彼は本棚から何冊かの本を抜き出してはまた戻していた。コーヒーを飲みながら、キャンバスの包みがまだ解いていないことや、この前買ったCDのことなどを静かに話した。コーヒーがまだ冷めないうちに彼はカップを空にして「今日はこの本を借りに来たんだ」と立ち上がり一冊を手にした。
「雪が降る前に帰るよ」
「ああ」
戸口で彼を見送りながら、ありがとうとはやはり言わないことにした。そのために彼は本を借りてゆくのだ。
絵具の匂いが部屋にこもらないよう窓を細く開けていた。そこから時折雪が吹き込んでくる。傍らの紅茶もすぐに冷たくなったが、そんなことは気にならなかった。熱が高すぎて体が軽く感じられる時と同じ感覚だ。
何をしてもどんなことがあっても、結局僕の行き着く先は、描くというひとつの作業に帰るのだった。この数箇月には辿り着けなかった心地好さに支配されて、ただ欲しい色を求めて絵具を混ぜ続けた。白い画面が徐々に絵具に埋められていくのと、それとは逆に外の景色が白い雪に消し去られていくのが、時間の経過を示していた。けれども僕にはそれさえ作業に組み込まれた一部に過ぎない。すべてが僕の中にあるような高揚感、何もかもを忘れて絵に没頭することの充足感。
(違う)
なぜかそう思って筆を置いた。
窓の向こうで雪がはらはらと落ちている。僕は立ち上がり、コートを手にして部屋を後にした。傘を忘れたことに気づいたが、取りに戻るのが面倒だった。タイヤの跡に沿ってゆっくりと歩き出す。
たった今まで満ち足りていた心地が冷えてゆく。両手をポケットに入れて俯いた。
誰も責めてはくれない。楽しくさえ感じられた時間を、申し訳なく思った。
僕は、きみを、忘れてしまうのだろうか。
考えてみるのも怖かった。習慣のまま乗り込んだ地下鉄の暖かなシートで、僕はずっと目を閉じていた。
地上から吹き込む雪が駅の階段を濡らしていた。踊場から見上げると入口の蛍光灯が眩しく、夕闇さえ淡く滲んでいた。冷たい空気が耳を打つ。雪は運河の波間に、タイルの舗道に、結晶模様を刻むかのように落ち続けて誰の眼にも映らないまま消えてゆくのだった。
僕を追い越してゆく車の尾燈の赤い眼も、すれちがう男の傘の下の眼も僕には無関心だったし、俯いて歩く僕もまた同じだった。ただひとり、きみが責めてくれるのならいいのにと頭の後ろの遠くで思っていた。
それで意味もなく扉を叩いた。
「はい」と返事があって、あらためて窓が明るいのに気がついた。自分の間抜けさにノックした右手を下ろすことも忘れてきょろきょろとした。扉を開けたのは、丸顔に大きな丸い目の男で、少年という風情の顔に伸びかけた髭がアンバランスで愛嬌があった。
「すみません、間違えました」
そう言って頭を下げると、彼は「もしかして、前に住んでいた方じゃありませんか」と言った。
「いいえ」
「じゃあ、前に住んでいた方のお知り合いでしょう」
「はい。でもどうして」
「ちょうどよかった。入ってください」
旧知の仲とでもいうような笑顔で彼は半ば強引に招き入れた。「先週越してきたんです」という言葉の通り、床に置かれているのはテレビと電話機、段ボールがふたつとその上に無造作に脱ぎ捨てたジャケット。部屋の隅には本が積み上げられ、その隣には本の一頁を額装して立て掛けてある。マチスだ。
部屋を見回している間に彼は手際よく紅茶をいれた。段ボールのひとつを真中に据えて、熱い紅茶の載ったトレイを置いて僕を見ると、もうひとつの段ボールからタオルを出して、黙って手渡した。
「どうしてわかったんですか」
「そこの、作り付けの棚の下のひきだしから、写真が出てきたんですよ」
彼は壁によりかかって座るとカップを手にした。
「前の住人の物だとは思ったんだけど、忘れていったというのも不自然だし。捨てていったんだなと思って。でも僕が勝手に処分していいのか、ちょっと迷ってたら」
「本人が現れた」
「でもそんな気がしてたから」
僕らは笑った。
「前の人の家に送ろうか、とも思ったんだけど。それもできないようだったから」
「知ってるんだ」
「いいえ」
そう言うと、彼は煙草をくわえて黙り込んだ。もう喋る気はないよ、という意思表示。僕も彼に倣った。
景色が違う。塗り替えられた真白の壁も。今は彼の部屋の顔をした景色が、僕を取り囲んでいる。玄関を振り返ると、見慣れた筈の扉さえ真新しく見えた。
紅茶の礼を言って立ち上がると、彼はひきだしから写真を取り出した。
「この写真は君の部屋で撮ったの?」
「そう」
「この本棚の二段目のこれ、ちょうど読みたいと思ってて」いたずらっぽい笑い。
「今これ、友達に貸してるんだ」僕も笑った。「戻ったら電話しようか」
そこで僕らは初めて自己紹介をし、電話番号を交換した。きみがこの部屋に残したのはとんでもないものだったと苦笑した。
偶然なのはわかっていた。
けれども、後から誰かが、必然と名付けるのかも知れない。天の配剤だとか、運命だとか呼ぶのかもしれない。僕がそれを何と呼ぶのか、まだ知らないけれど。
キャンバスの包みを抱えて、時計屋の重い扉を背中で押した。愛想のいい親父が拭き終えた眼鏡をかけなおして迎えた。僕は荷物を床に降ろし、ポケットから腕時計を取り出して見せた。
「直りますか」
「中はね、すぐ直るけど。針とガラスは代えないとね」
「そのままがいいんですけど」
「ええ?」親父は顔を上げた。
「変わってんねえ、あんた。ま、そういうこともあるだろうさ」
親父が時計を直している間、少しずつ話した。事故っちゃってね、その時壊れて。そうかい大変だったね。でも大事な時計だから変えたくないんだ。そうかい、そういうこともあるな。
右の手首に懐かしい重みが戻った。それさえすぐに忘れてしまうのだろう。そして時刻を確かめるたびに、また思い出す。忘却の川底に堆積する石のように、すべての記憶が見えなくなり、それでもそこにあるように。
僕の時間は再び動き出した。